宅建試験を受けてきました。せっかく受けてきたので、試験について簡単にまとめてみました。これから受ける人の参考になれば幸いです。
宅建士を受験した理由
大きく分けて三つの理由があります。
知識の更新
一つ目は、2020年4月に民法改正が行われましたが、改正により旧民法と新民法では結論が変わってしまうようなものも有り、知識のブラッシュアップを目的に受験しました。
改正例
- 錯誤無効⇒錯誤取り消し
- 法定利率の改正(5%→変動金利)
- 消滅時効期間の変更
- 建物建築等の請負の契約解除制限がなくなった など
特に「4」は旧民法では解除できなかったものが新民法では解除できるようになりました。
※詳しくは法務省パンフレット(PDF)
不動産関連知識の整理
二つ目は、今の仕事(融資業務)でも不動産担保などを扱うので、不動産関連の知識は無いと出来ません。これまでも実務でためてきた知識を整理をしてみようと思いました。
自分の不動産投資の為
三つめは、自身でも現物の不動産投資をしていますが、将来的にはもう少し大きな投資をしてみたいので、自分が投資をする際の基礎知識がほしかったのも理由です。
↓私が実践した短期合格法はこちら

宅建士試験の内容について
試験形式
- 解答方法:四択・マークシート方式
- 試験時間:2時間
- 出題範囲:全50問(民法14問、宅建業法20問、法令上の制限8問、その他8問)
法令上の制限は建築基準法や都市計画法、国土法など不動産の利用方法を制限する法律から出ます。
その他は不動産に関わる税金や統計などから出ます。
不動産業者に勤めている人は講習を受けるとその他が5問免除になります。
- 試験日:毎年1回(10月)
ざっくりいうと、民法30%、宅建業法40%、法令上の制限15%、その他15%です。
合格ラインは毎年異なっており、15~18%の間で調整がなされています。
| 年度 | 合格基準点(一般受験者) | 合格率 |
|---|---|---|
| 2014年 | 32点 | 17.5% |
| 2015年 | 31点 | 15.4% |
| 2016年 | 35点 | 15.4% |
| 2017年 | 35点 | 15.6% |
| 2018年 | 37点 | 15.6% |
| 2019年 | 35点 | 17.0% |
| 2020年 | 38点(2020年10月試験)
36点(2020年12月試験) |
17.6%(10月)
13.1%(12月) |
| 2021年 | 34点(2021年10月試験) | 17.9%(10月) |
宅建士試験の難易度
難易度は10段階評価すると「6」、「普通~やや難」だと思います。
私の場合、スタディプラスというアプリで勉強時間を記録していまして、勉強時間は150時間弱、8月頃から始めて得点は45点(自己採点)でした。(2020年10月試験を受験しました)
資格予備校などでは勉強時間は250~300時間程度とされているようです。この時間は不動産や法律の予備知識の有無でずいぶん変わるなという印象です。私の場合は職業柄、民法や不動産の基礎知識は有ったので時間短縮につながったと思います。
また、宅建は毎年20万人以上が受ける人気試験なだけあって、教材がとても充実しています。スマホアプリも沢山有るので、勉強はしやすい試験と言えます。
私が保有している他の資格試験と比べると、
- FP2級の2~3倍
- 中小企業診断士 1次試験の2科目分
- 日商簿記3級の3~4倍
- 日商簿記2級の1.5~2倍
- 初級シスアドの3~4倍
くらいの難易度だったと思います。
↓こちらの記事では日商簿記2級と難易度比較を行っています。
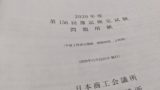
宅建士でなければできないこと
不動産業者の関わる不動産売買・賃貸の仲介などは、法律で色々と制限されています。
重要事項説明書(35条書面)や契約内容を確認する文書(37条書面)への記名・押印は宅建士でなければなりません。
不動産売買・賃貸借の時に作成・交付するお客さんに対する重要事項説明書の説明は宅建士がしなければなりません(宅建士以外がやってはダメ)。
また、不動産業者には5人に1人は宅建士を置かなければなりません(必置資格)。不動産業は宅建士が居なければ仕事にならない(仕事が出来ない)という事ですね。
宅建士は役に立つか?
結論はYESです。
ご自身で不動産屋を独立開業する事が出来ます。サラリーマンでも不動産屋では必置資格なので需要が無くなる事は有りません。世間的に認知度の高い資格で履歴書にも書けるレベルの資格なので、ある程度の評価は得られます。勉強内容も民法などは役に立ちますし、不動産関連の知識は自分が家を買うときや不動産投資を考える時にも役に立つと思います。非常に有用性の高い資格です。
↓私が実践した短期合格法はこちら












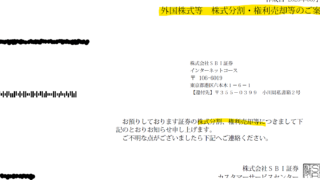



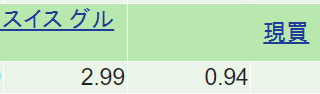






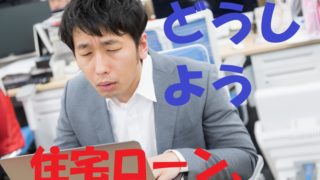

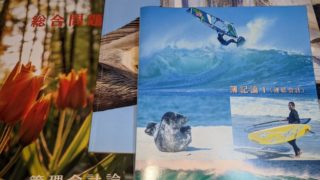


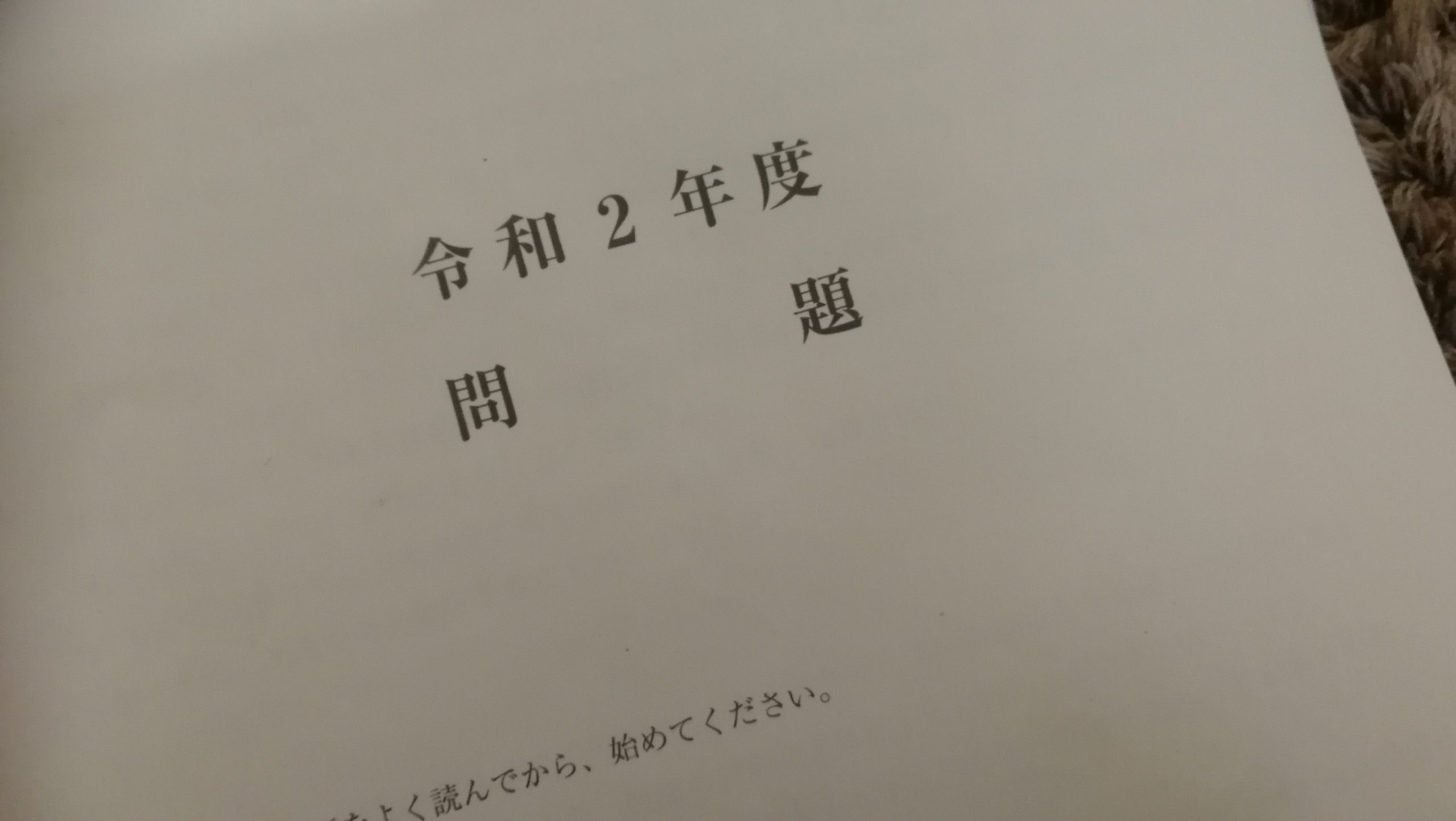
コメント