こんにちは、くろたろうです。
第三回の今日は銀行の種類や役割についてまとめてみます。
銀行シリーズ
第一回:あなたの取引銀行大丈夫? 経済が好調な今だからリスクを考える
第二回:銀行の健全性をまとめてみた 金融機関の安全性はどこを見ればいいの?
第三回:都銀、地銀、信金は何が違うの? 金融機関の種類と存在意義
第四回:個人の取引銀行選び 複数行取引で便利さと身近さを確保しよう
第五回:個人のATMと振込を無料にする 銀行の特典をフル活用しよう
第六回:経営者の取引銀行選び 取引銀行に求めるのは金利で良いのですか?
都銀、地銀、信金のプロフィール
都銀(都市銀行)
都市銀行を略して都銀。
都銀といったらとにかくでかくて日本全国どこにでもあるイメージではないでしょうか。
まさに日本経済を支えるような大きな銀行でした。
- かつて存在した都銀
第一勧業銀行、三井銀行、富士銀行、三菱銀行、協和銀行、三和銀行、住友銀行、大和銀行、東海銀行、北海道拓殖銀行、太陽神戸銀行、東京銀行、埼玉銀行
都銀はバブル崩壊後、比率でみると実は最も減った銀行です。
今では都市銀行はほとんどが集約されてみずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行の3行(メガバンク)と、りそな銀行の合計4行になりました。
ドラマなどではメガバンクというと日本経済を支えるような大企業を相手にして融資をしたりしている花形のイメージがあります。一方で殿様のイメージもあり、苦しい中小企業の融資を断って社長を自殺に追い込んでいるイメージがあります。(実際に中小企業のメインバンクにはなりえないと思います。)
ドラマの半沢直樹やハゲタカではそういった描写があります。これらの作品は非常に面白いです。
実際にメガバンク等都銀は全国展開しており日本国民全員を顧客としています。活躍の場は日本だけにとどまらず、海外進出も積極的に行っています。また、法人取引では誰もが知る大企業を主要顧客とし、日本経済を支える役目を担っています。メガバンクがダメになると日本政府も一般個人もみんな困ります。一方で「やたらエラそう」、「融通が利かない」といった印象を持っている方も多いのは事実です。
地銀(地方銀行)
地方銀行を略して地銀。
地銀は実は地方銀行(64行)と第二地方銀行(40行)に分かれています。(紛らわしいので第一地銀と第二地銀といいます。)
名前は同じ「銀行」なのですが、第一地銀は「全国地方銀行協会」の会員、第二地銀は「第二地方銀行協会」の会員で金融庁の登録も違います。また、第二地銀は殆どが相互銀行という業態から銀行に転換しています。
第一地銀は地元の有力地銀であることが多く、「殿様地銀」などと言われる事があります。その名の通り地域において多大なシェアを持っており、地域経済に大きな影響力を持っている銀行も多いです。
第二地銀は中小企業を主にしていた相互銀行から普通銀行に転換しており、第一地銀に比べて規模が小さかったり、経営内容がぜい弱だったりします。地域では地銀に次いで二番手、三番手だったりします。
第一地銀も第二地銀も同じ銀行法で成りたっているので出来る業務に違いはありません。
また、どちらも地方に拠点を置いて地域の名前(福岡とか千葉とか)を付けた銀行が多いですが、その地域で営業しないといけない義務はありません。東京でも大阪でも海外でも好きなところに進出できます。従って、広域支店網を持つ地銀も少なくありません。
以前は第二地銀よりも地銀の方がエライという風潮が地銀業界内にはありました。
しかし最近は第二地銀も規模の大きなところが増え、正直第一地銀も第二地銀も大した違いは無くなってきています。
信金(信用金庫)
信用金庫を略して信金。
多くが元々は信用組合で、信用金庫法が施行されたときに信用組合から業態転換したところが信用金庫になりました。信用金庫に業態転換しなかったところは信用組合のまま今も残っています。
信金は地銀よりも営業地域が狭く、「信用金庫法」という法令を基に営業しています。
実は信金は法令の制限で信金ごとに決められた営業地域の外に支店を出したりする事が出来ません。また、決められた営業エリアに関わりのない企業や個人に融資を行うこともできません。自分の営業地域がどんどん衰退するからといって、海外には出れないし、東京や大阪、福岡などの大都市に支店を作る事は出来ません。決められた営業地域と運命共同体の金融機関です。地域の企業や個人が立ち行かなくなる≒自分自身が潰れるという構図が成り立ちます。そのような理由から、地域経済や地域社会に対する姿勢は都銀とはもちろん、地銀とも一線を画しています。
ドラマなどでは都銀や地銀が見捨てた中小企業を信金が融資して助けてたりします。最後の貸し手といわれることもあります。中小企業や自営業者は信金と上手にお付き合いすることをお勧めします。
都銀、地銀、信金は何が違うの?
それぞれの違いについて1.取扱業務、2.営業エリア、3.地域密着度、4.規模の3つの視点で見ていきましょう。
取扱業務
一般個人が使う上ではほとんど変わりありませんが、細かいところに違いがあります。
銀行や信金の取扱業務は預金業務、為替業務(振込等)、融資業務が三大業務といわれています。
- 預金業務と為替業務についてはほとんど違いがありません。
・地銀や信金の営業エリア外の人は口座開設を断られることがあります。
・地銀・信金は支店が無い県や市の税金の取り扱いができない場合があります。口座振替を設定したくてもできなかった、なんてケースもあるようです。
・外国送金等海外業務は圧倒的にメガバンクが強いです。地域銀行にはメガバンクの送金システムを利用しているところも多数あります。
・また、ネットバンクなどの新興銀行は企業の収納機関(要は利用料金の口座振替)に登録されていないところもあるので、料金の引き落としに口座が使えないケースもあります。
- 融資業務においては大きな違いがあります。
- 都銀⇒貸出の制限なし
制限はないものの、大企業や売上高50億円以上の中小企業としか取引をしないと豪語する支店も都内の一部店舗ではあるようです。実質的に中小企業の小の方はよい対応を望めません。また、「貸し渋り」や「貸しはがし」という言葉が作られる原因を作ったのは都銀です。経済情勢に応じて融資スタンスがドラスティックに変化するので注意しましょう。
最近は国内は儲からないので、海外向けに貸出を大きく増やしています。海外に子会社や主要取引があるような中堅以上の企業には必要とされる銀行といえます。
- 地銀⇒貸出の制限なし
都銀と同じく制限はなく、貸せるところにはどんどん貸すという感じです。本店所在地が地方だけれど貸出が伸ばせそうな東京や大阪などの大都市に積極的に進出している地銀は「出稼ぎ地銀」と言われます。出稼ぎ地銀の東京支店などは上場企業~中堅企業までしか相手にしていないところが多いです。出稼ぎ地銀の融資スタンスは本店のある地元の融資残高と出稼ぎ先(東京など)での融資残高の融資バランスを取るために都度変化します。例えば東京の融資が伸びすぎると地元と東京の融資バランス(比率)が悪くなるため、東京の融資残高を減らすことがあります。ある地銀の東京支店では融資のマイナス目標(融資を減らす目標)を設定されたことがあるそうです。また、出稼ぎに来ているので損は出来ません。従って、企業業績が悪くなるとすぐに融資を引くので注意しましょう。
悪い事をたくさん書きましたが出稼ぎにきた地銀はこういうスタンスなのです。地銀と付き合う場合は地元の地銀と付き合いましょう。
- 信金⇒貸出の制限あり
1.法人は資本金9億円以下または従業員数300人以下である事
2.法人は信金の営業地域内に本店・支店・営業所がある事
3.個人は信金の営業地域内に住居または勤務先がある事
読むだけで面倒な制約があるのが信用金庫です。信金は少額融資の場合(700万円以下)を除いて「出資会員」にしか融資ができません。その出資会員になるためには上記3つを満たしていなければなりません。
会社の大きさと立地で貸し出しが制限されています。しかも営業エリアが決められているので貸出先もおのずと限られてきます。地元にある企業に安定した取引をする傾向にあります。ただし、信金は規模が小さいところが多いので、多額の融資を行う事は出来ない場合があります。また、信金は地元の悪い内容の会社も支えないといけないので、都銀・地銀と比べると金利は高めです。
「信用金庫」と「信用組合」「銀行」の主な相違点
区分 信用金庫 信用組合 銀行 根拠法 信用金庫法 中小企業等協同組合法
協同組合による金融事業に
関する法律(協金法)銀行法 設立目的 国民大衆のために金融の円
滑を図り、その貯蓄の増強
に資する組合員の相互扶助を目的と
し、組合員の経済的地位の
向上を図る国民大衆のために金融の
円滑を図る組織 会員の出資による協同組
織の非営利法人組合員の出資による協同組
織の非営利法人株式会社組織の営利法人 会員(組合員)
資格(地区内において)
住所または居所を有する者
事業所を有する者
勤労に従事する者
事業所を有する者の役員
<事業者の場合>
従業員300人以下または資
本金9億円以下の事業者(地区内において)
住所または居所を有する者
事業を行う小規模の事業者
勤労に従事する者
事業を行う小規模の事業者
の役員
<事業者の場合>
従業員300人以下または資
本金3億円以下の事業者(卸
売業は100人または1億
円、小売業は50人または5
千万円、サービス業は100
人または5千万円)なし 業務範囲
(預金・貸出金)預金は制限なし
融資は原則として会員を対
象とするが、制限つきで会
員外貸出もできる
(卒業生金融あり)預金は原則として組合員を
対象とするが、総預金額の
20%まで員外預金が認めら
れる
融資は原則として組合員を
対象とするが、制限つきで
組合員でないものに貸出が
できる(卒業生金融なし)制限なし 一般社団法人全国信用金庫協会「信用金庫と銀行・信用組合との違い」より
営業エリア
広い 都銀>>>>地銀>>信金 狭い
- 都銀は国内のみならず海外支店もありグローバルに展開しています。三菱UFJ銀行など一部のメガバンクは海外銀行を子会社として傘下に収めているケースもあるので、海外業務は国内最強です。
- 地銀は地元はあるもののそれを飛び越して展開しているので広いです。海外支店や海外駐在事務所がある利銀もあります。
- 信金は決められた営業エリアからは出られないので狭いです。ただし取引先の海外業務支援や海外情報収集のために海外駐在事務所を持っている信金はあります。
地域密着度
地域密着 信金>>>地銀>>>>>都銀 関係希薄
- 信金は営業エリアが決まっているので、地元の中でしか商売ができません。従って、地元のイベントには積極的に参加しています。信金職員もその地域出身の人が多いです。地域密着度合いでいうと一番高いです。
- 地銀も信金同様に地域密着度は高いです。しかし、出稼ぎ地銀などと言われ、地元を離れていってしまう地銀が増えてきました。行員も地元の人が多かったのですが、営業エリアが地元以外に広がっているのでいろいろな地域の人が増えています。地域密着度は徐々に低下してきています。
- 都銀はまず地域のイベントに出てくることはありません。お金を出して協賛する事があるくらいでしょう。全国展開しており人事異動も短期間で行われます。採用も全国採用なので、いろいろな人が入れ代わり立ち代わりに来ます。密着度は最も低いといえるでしょう。
規模
都銀>>地銀>信金
一般的には都銀が大きく、地銀、信金と続きます。
規模については、地銀も信金も大規模化が進んでおり、銀行だから大きい、信金だから小さいとは言えなくなってきています。
詳しくはこちら↓



所有者は誰か
- 銀行⇒株式会社であるため、株主が所有者である営利企業
都銀も地銀も「銀行」と名がつくところは全て「株式会社」です。株式会社は株主が出資をして設立した営利企業です。株主に利益を還元しなければ経営が成り立ちません。保有株式に応じて議決権というものを持っています。従って、銀行は株主のものです。
株式会社については↓記事へ。

- 信金⇒協同組織であるため、利用者が所有者である非営利企業
信金は地域住民がお金を出しあって作った協同組織金融機関です。昔はお金が不足していたので、お金が余っている人から不足している人に融通するために作られたのが基になっています。信金にも総会とか総代会という株主総会に似た制度があります。株式会社は一株一議決権ですが、信金は一人一議決権なので、利用者(出資会員)一人一人が金額に関係なく平等な所有者ということになります。
また、株式会社の銀行と違って営利を主目的としていません(営利と非営利の中間の存在なので、中間法人といいます)。
まとめ
鋭い人だと「結局のところ都銀だけあれば良くね?」と思う事でしょう。
でも、銀行、信金は成り立った歴史が全然違います。経営者や経理部長、サラリーマン、主婦などそれぞれの立場で特徴を見ながらお付き合いをしましょう。
都銀
- 13あった都銀が集約されて出来た
- 日本を代表する大企業がメインの顧客
- 全国に支店があって便利
地銀
- 地元経済を支える企業に資金を提供する。
- 第二地銀は地元の中小企業を主な顧客としていた相互銀行がもとになっている。
- 地元を中心に県外にも支店を構える
信金
- 地元の人が地元の人の為に作った金融機関。
- 最後の貸し手といわれることもある
- 地元にしか支店が無い



















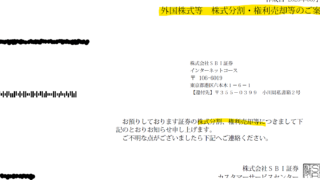

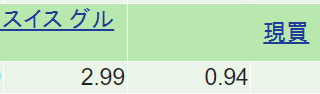





コメント